「ジャズ・アイコン、ジャズのレジェンド。そして音がでかい」──『『最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生』発刊記念イベント・レポート
2021年9月25日(土)@ 東京・四谷 いーぐる


写真左から村井康司氏、池上信次氏
■日時/会場:2021年9月25日(土)/ 東京・四谷 いーぐる
■トーク出演
池上信次さん(書籍編集者)、村井康司さん(音楽評論家)、丸山京子さん(通訳・本書翻訳・リモート出演)
『「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生』発刊記念イベント「〜音でたどるロン・カーターの半生〜」が9月25日、東京・四谷いーぐるにて開催された。当日はロンの音源を聴きながら、池上信次さん(書籍編集者)、村井康司さん(音楽評論家)の登壇、丸山京子さん(通訳・本書翻訳)がリモートで参加する形で進められた。

*丸山京子さんが語るロン・カーターの人物像
池上信次(以下池上):本日進行を務めさせていただきます書籍編集者の池上です、そして音楽評論家の村井康司さんです。
村井康司(以下村井):よろしくお願いいたします。この本の巻末の解説とインタビューをやらせていただきました。
池上:この本『Ron Carte r: Finding The Right Notes』」の初版はアメリカで2014年に発売され、今回の日本語版は2017年の最新版の全訳です。ロン・カーターが、『ダウンビート』誌、『ビルボード』誌にも寄稿している著者ダン・ウーレットに全面協力した本なので、自伝といってもいいものです。取材したアーティストもジャズのレジェンドからヒップホップ・アーティストまで幅広くずらりと顔を揃え、ロンの知られざるエピソードも数多く掲載されています。そして、この本の翻訳をされたのが丸山京子さん。今日はリモート出演ということで、お呼びしたいと思います。丸山さんはロック、ポップス、ジャズと多岐にわたるジャンルの来日ミュージシャンの通訳を35年以上されていて、同時に膨大な音楽関係書の翻訳をされていらっしゃいます。そしてロン:カーター本人とも親交があってその人となりを大変よく知る方なので、その知られざる部分のお話も伺えればと思っています。
村井:よろしくお願いします。
池上信次(以下池上):本日進行を務めさせていただきます書籍編集者の池上です、そして音楽評論家の村井康司さんです。
村井康司(以下村井):よろしくお願いいたします。この本の巻末の解説とインタビューをやらせていただきました。
池上:この本『Ron Carte r: Finding The Right Notes』」の初版はアメリカで2014年に発売され、今回の日本語版は2017年の最新版の全訳です。ロン・カーターが、『ダウンビート』誌、『ビルボード』誌にも寄稿している著者ダン・ウーレットに全面協力した本なので、自伝といってもいいものです。取材したアーティストもジャズのレジェンドからヒップホップ・アーティストまで幅広くずらりと顔を揃え、ロンの知られざるエピソードも数多く掲載されています。そして、この本の翻訳をされたのが丸山京子さん。今日はリモート出演ということで、お呼びしたいと思います。丸山さんはロック、ポップス、ジャズと多岐にわたるジャンルの来日ミュージシャンの通訳を35年以上されていて、同時に膨大な音楽関係書の翻訳をされていらっしゃいます。そしてロン:カーター本人とも親交があってその人となりを大変よく知る方なので、その知られざる部分のお話も伺えればと思っています。
村井:よろしくお願いします。

写真右端丸山京子氏
丸山京子(以下丸山):よろしくお願いいたします。
池上:この本の日本語版の出版が決まる前から、丸山さんはロン・カーターから本のことは聞かれていたそうですが。
丸山:ロンさんに通訳としてお会いしたのは『ディア・マイルス』(2006年)の頃で、その後来日の際には取材でご一緒しました。何度目かの来日のとき、この本の原書を渡されて、「こういう本が出たんだけど、誰か日本で訳して出したい人はいるかな? まず読んでみてくれないかな」と。私に訳せとは言わないんです(笑)。原書も430ページくらいあるので読むのは大変だな……と思いながら引き気味に預かりました。最初は会うたびに「読んだか?」と訊かれたんですけど、そのうちに訊かれなくなった──でも私の心の中では常にこの本のことはあって。その後ロン・カーター・ノネット(2016年)の頃またお会いする機会があったので、今回こそ「読んだ」と言おうと思ったんです。で、それを証明する方法として、ロンさんがすごい甘党だと本に書いてあったので好物だという “Fig Newtons” というビスケットの中にドライイチジクが入ったお菓子を持っていって、「お好きだと本に書いてありましたね」と渡したんです。そうこうするうちにこのエピソードをご存知ない編集の方から翻訳のオファーがあって、これは運命なのかな──とお引き受けしました。
池上:ロンさんには日本語版の翻訳をしたということはお話しされました?
丸山:コロナ禍の最中なので、来日もされてないしお会いしてなくて。村井さんのインタビューの電話通訳をしたときも、まだ翻訳をすることは決まってなかったのでお話ししてないです。
池上:丸山さんがロンさんと接していて、他のミュージシャンとの違いを感じられるところはありますか?
丸山:私がロンさんとお仕事をするようになってから、他のミュージシャンの方とは違っていつもお一人で、マネージャーさんと一緒に来日されたことがないんです。だからインタビューだけじゃなく、マネージメントのことも全部ご自分でやられて、すごくロンさんらしい。本の中にも出てきますけど、単に音楽を演奏していれば楽しい〜というタイプの方ではないようですね。ミュージシャンとして得るべき地位や立場、ギャラ(笑)とか、自分でやるべきことは自分でやる──そしてリスペクトを得るという方かなと。
池上:真面目っていうこと。
丸山:一言で言うとかなり真面目ですけど、真顔でジョークを言ったり、半分相手を見てからかってるな──というのが慣れてくると分かってきました。
池上:来日時にレコード店に行ったという話も。
丸山:テレビの取材でディスクユニオンに通訳で一緒に行きました。基本的に自分が関わったLPのところに行って。
池上:実際のロンさんと、本に書かれているロンさんとのズレを感じる部分はありますか?
池上:真面目っていうこと。
丸山:一言で言うとかなり真面目ですけど、真顔でジョークを言ったり、半分相手を見てからかってるな──というのが慣れてくると分かってきました。
池上:来日時にレコード店に行ったという話も。
丸山:テレビの取材でディスクユニオンに通訳で一緒に行きました。基本的に自分が関わったLPのところに行って。
池上:実際のロンさんと、本に書かれているロンさんとのズレを感じる部分はありますか?

丸山:いや、ズレどころか、これを読んでいるとロンさんの言葉が聞こえてくるようで、特に彼の言葉を引用したところや、筆者がロンさんのニューヨークのアパートに行ってインタビューに至るまでのくだりとか、その現場が目に浮かぶようです。この本を訳すときにタイトルの「Finding The Right Notes」の “Note” をどう訳すか──〈音〉って訳すとサウンドの〈音〉だけになってしまうけど、この “Note” はひとつひとつの音で、ロンさんはこの「正しい音」という言い方をインタビューでもよくされてるんです。あと、自分のレパートリーを “library” と言われる方ってあまりいないと思うんですけど、その言い方もこの本でも何度も使われて、ロンさん独自の言葉だな──って思いました。ズレはないですね──。あ、でも本の中では奥様の亡くなられた時のことも詳しく書かれてますけど、私はそういうプライヴェートの話は一切聞いたことはなかったです。だから、この本でしか知ることができないこともたくさんあると思います。
池上:ロンさんのすべてがここにある。
丸山:本の最後にある一問一答はロンさんのお茶目な部分がでてくる回答だと思います。あんな感じで、普通に喋ってるとちょっと冗談っぽいことも言ったりもする方なので、本をずっと読んでると真面目一本の印象なんですけど、最後に人間っぽいところが出てくるなぁと思いました。
村井:ロンは年下のミュージシャン、ビル・フリゼールやジョーイ・バロンからものすごくリスペクトされてますね。
丸山:最近では女性ジャズ・ハーピストのブランディー・ヤンガーの新作にもロンさんは参加されてます。彼女がインタビューの中でロンさんが参加してくれたことをすごく喜んで話された記事で、印象的だったこととして〈A♭より下の音を弾くな、その和音のルートを弾くな〉と言われたことをあげてます。最初は意味が分からなかったそうですが、後から〈その音の下はベースの音で自分の領域だから、そこに入ってくるな〉ということだと言われて、彼女は目から鱗が落ちたそうです。私はなぜそれに気がつかなかったんだろう──と。そうやって若い人がハッと思うことを的確に言える人なんだと思います。きちんとすればきちんと返してくれる──皆さんも同じように仰いますけど、私もちょっと学校の先生に会っているような気分にいつもなります(笑)。心地よい緊張感があるというか。ご自身も実際に大学で教えられているので、そういうことが元々向いてる気質なのかも。
池上:僕たちはなかなかそういう面でミュージシャンの方と直接触れ合うことが少ないので、今のお話でこの本に書かれていることが実際にロンさんの人物像なんだとわかりました。
丸山:あ、最後にもうひとつ。ロンさんオシャレです。オシャレにはめちゃめちゃ気をつかってます。普段からスカーフや、ポケットチーフ、ネクタイとかにもすごく拘りがあるし、ニューヨークのマンションにもいろいろな絵が飾ってあって美しいものに対する意識の強い方だと思います。
池上:では、この辺りで丸山さんのコーナーは終了ということで、どうもありがとうございました。(場内大拍手)
丸山:ありがとうございました。
*ロン・カーターの人生:キャリアを追う
池上:ロンさんのすべてがここにある。
丸山:本の最後にある一問一答はロンさんのお茶目な部分がでてくる回答だと思います。あんな感じで、普通に喋ってるとちょっと冗談っぽいことも言ったりもする方なので、本をずっと読んでると真面目一本の印象なんですけど、最後に人間っぽいところが出てくるなぁと思いました。
村井:ロンは年下のミュージシャン、ビル・フリゼールやジョーイ・バロンからものすごくリスペクトされてますね。
丸山:最近では女性ジャズ・ハーピストのブランディー・ヤンガーの新作にもロンさんは参加されてます。彼女がインタビューの中でロンさんが参加してくれたことをすごく喜んで話された記事で、印象的だったこととして〈A♭より下の音を弾くな、その和音のルートを弾くな〉と言われたことをあげてます。最初は意味が分からなかったそうですが、後から〈その音の下はベースの音で自分の領域だから、そこに入ってくるな〉ということだと言われて、彼女は目から鱗が落ちたそうです。私はなぜそれに気がつかなかったんだろう──と。そうやって若い人がハッと思うことを的確に言える人なんだと思います。きちんとすればきちんと返してくれる──皆さんも同じように仰いますけど、私もちょっと学校の先生に会っているような気分にいつもなります(笑)。心地よい緊張感があるというか。ご自身も実際に大学で教えられているので、そういうことが元々向いてる気質なのかも。
池上:僕たちはなかなかそういう面でミュージシャンの方と直接触れ合うことが少ないので、今のお話でこの本に書かれていることが実際にロンさんの人物像なんだとわかりました。
丸山:あ、最後にもうひとつ。ロンさんオシャレです。オシャレにはめちゃめちゃ気をつかってます。普段からスカーフや、ポケットチーフ、ネクタイとかにもすごく拘りがあるし、ニューヨークのマンションにもいろいろな絵が飾ってあって美しいものに対する意識の強い方だと思います。
池上:では、この辺りで丸山さんのコーナーは終了ということで、どうもありがとうございました。(場内大拍手)
丸山:ありがとうございました。
*ロン・カーターの人生:キャリアを追う

村井:この後はロン・カーターのリーダー作、参加作を聴きながら、本に即してロン・カーターの音楽的な半生を辿っていきたいと思います
池上:本にも書かれてますが、1937年に生まれたロン・カーターは最初チェロから始めてベースに移るんですね。
村井:ロン・カーターは本当にクラシックの人なんです。デトロイトのキャス・テック(キャス・テクニカル高校)でチェロを、それからニューヨーク州のイーストマン音楽院でクラシックのコントラバスを学ぶ。ジャズはその後。
池上:クラシックで名を上げようと活動してたんですけど、有色人種はオーケストラにはいらない──と言われて諦めざるを得なかった。
村井:ここがロン・カーターを考えるときに重要なポイントで、言われた相手が超一流の指揮者ストコフスキー。当時アメリカ、ヒューストンのオーケストラの指揮者だったストコフスキーに、「君はなかなか素晴らしい、しかしテキサス州では有色人種をオーケストラに入れることに理事たちは困惑するのでダメだ」と言われて。それでしょうがないのでジャズをやる……ところから始まったんです。クラシックに対する彼の思いは今でもすごく強くて、ショックも大きかったんでしょう、2000年代になっても「アメリカの5大オーケストラにアフリカン=アメリカンが何人いる? ほとんどいないだろう」って言ってるんです。
池上:クラシックを諦めてジャズ……ですから。最初のアルバムでチェロを弾いているのは当たり前というか。
村井:彼は1960年頃からニューヨークに出てきてジャズのミュージシャンとして活動して、一番最初に注目されたのはエリック・ドルフィーの『アウト・ゼア』というアルバム。ここではベースではなく全部チェロ。その翌年に出た最初のリーダー・アルバム『ホエア?』でも、ベースも弾いてますが主にチェロを弾いてます。どちらもベーシストが別にいて、そのどちらもがジョージ・デュヴィヴィエ。ロンはジョージ・デュヴィヴィエのことは先輩として尊敬しています。
池上:では早速それを聴いていきましょう。
村井:エリック・ドルフィーの『アウト・ゼア』(1961年)からタイトル曲の「アウト・ゼア」。ここではロン・カーターはチェロを弾いています。
池上:本にも書かれてますが、1937年に生まれたロン・カーターは最初チェロから始めてベースに移るんですね。
村井:ロン・カーターは本当にクラシックの人なんです。デトロイトのキャス・テック(キャス・テクニカル高校)でチェロを、それからニューヨーク州のイーストマン音楽院でクラシックのコントラバスを学ぶ。ジャズはその後。
池上:クラシックで名を上げようと活動してたんですけど、有色人種はオーケストラにはいらない──と言われて諦めざるを得なかった。
村井:ここがロン・カーターを考えるときに重要なポイントで、言われた相手が超一流の指揮者ストコフスキー。当時アメリカ、ヒューストンのオーケストラの指揮者だったストコフスキーに、「君はなかなか素晴らしい、しかしテキサス州では有色人種をオーケストラに入れることに理事たちは困惑するのでダメだ」と言われて。それでしょうがないのでジャズをやる……ところから始まったんです。クラシックに対する彼の思いは今でもすごく強くて、ショックも大きかったんでしょう、2000年代になっても「アメリカの5大オーケストラにアフリカン=アメリカンが何人いる? ほとんどいないだろう」って言ってるんです。
池上:クラシックを諦めてジャズ……ですから。最初のアルバムでチェロを弾いているのは当たり前というか。
村井:彼は1960年頃からニューヨークに出てきてジャズのミュージシャンとして活動して、一番最初に注目されたのはエリック・ドルフィーの『アウト・ゼア』というアルバム。ここではベースではなく全部チェロ。その翌年に出た最初のリーダー・アルバム『ホエア?』でも、ベースも弾いてますが主にチェロを弾いてます。どちらもベーシストが別にいて、そのどちらもがジョージ・デュヴィヴィエ。ロンはジョージ・デュヴィヴィエのことは先輩として尊敬しています。
池上:では早速それを聴いていきましょう。
村井:エリック・ドルフィーの『アウト・ゼア』(1961年)からタイトル曲の「アウト・ゼア」。ここではロン・カーターはチェロを弾いています。
♪「Out There」/『Out There』Eric Dolphy
村井:これを聴くと、登場してきたときからアヴァンギャルドなことに対して理解があって、多分ストラヴィンスキーとかバルトークが好きだったみたいということもある。チェロをベースではなくチェロのチューニングで弾いたジャズ・ミュージシャンって当時あまりいなかったところもドルフィーは気に入ったと思うんです。で、次にかける最初のリーダー作『ホエア?』(1961年)はこの『アウト・ゼア』の続編のような作りになっていて、非常にサウンドも似ていて、ロン・カーターはこういうエリック・ドルフィー的な音が大好き──というところからジャズ人生が始まったというのは興味深いところです。では初めてのリーダー作『ホエア?』から「ラリー」を。
♪「Rally」/『Where?』Ron Carter
村井:メンバーはロン・カーターに、エリック・ドルフィーがバス・クラリネット、ピアノがマル・ウォルドロン、ベースがジョージ・デュヴィヴィエ、ドラムはチャーリー・パーシップ。こういうアヴァンギャルドなことを平気でできる人なので、この後マイルス・バンドに入ってかなり過激なことをやっても平気だった。で、2枚目のリーダー作はずっと後の1969年に出ていて、マイルス・バンドにいる間はリーダー作は録音していない。仲間のハービー・ハンコックとかウェイン・ショーター、トニー・ウィリアムスもブルーノートから何枚もアルバムを出しているんです。今回ロンにインタビューをした際に、なぜ9年間リーダー作を作らなかったのかを聞いたら、〈誰も頼まなかったから〉と(笑)。〈ともかく忙しくて、マイルスの仕事やコマーシャルの仕事があるのでまったく作ろうと思ってなかった〉ということでした。マイルス・バンドを辞めてやっと時間ができたので作ったのが2枚目の『アップタウン・カンヴァセイション』。メンバーはハービー・ハンコックに、ヒューバート・ロウズがフルート 、ドラムはグラディ・テイトでほとんどオリジナル曲をやっています。では「リトル・ワルツ」を。これはロン・カーターお気に入りのオリジナル曲です。
♪「Little Waltz」/『Uptown Conversation』Ron Carter
村井:さっきコマーシャルの仕事が忙しかった──という話がありましたけど、ものすごく忙しかったみたいで、エレクトリック・ベースも普通に使っていたようですね。
池上:驚くことに一緒にやったベーシストのジョージ・デュヴィヴィエは、そのCMの仕事のナンバー・ワンの人だった。
村井:ジャズ・ミュージシャンが匿名で、テレビのジングルとかCMソングを山のようにやっていたんですね。どんな音楽もできるし譜面も読めるしということだと思います。リチャード・ディヴィスというベーシストも一緒にCMをやっていて、ジョージ・デュヴィヴィエ、ロン・カーターの三巨頭はアンプを持ってスタジオに行くのは大変なので、みんなでアンプを共同購入していろんなスタジオに置いていたということも本に書いてありました。では、次にマイルス・バンドですが、ロン・カーターが入るときのエピソードもこの本に書いてあります。簡単に入らなかった毅然とした態度がマイルスに気に入られたみたいです。では1964年2月のライヴ録音のマイルス・バンドの『フォー・アンド・モア』を。ハンコック、トニー・ウィリアムス、ロン・カーターが若さに任せて無茶苦茶なことをやりまくる最初期の音です。曲は「ソー・ホワット」。
池上:驚くことに一緒にやったベーシストのジョージ・デュヴィヴィエは、そのCMの仕事のナンバー・ワンの人だった。
村井:ジャズ・ミュージシャンが匿名で、テレビのジングルとかCMソングを山のようにやっていたんですね。どんな音楽もできるし譜面も読めるしということだと思います。リチャード・ディヴィスというベーシストも一緒にCMをやっていて、ジョージ・デュヴィヴィエ、ロン・カーターの三巨頭はアンプを持ってスタジオに行くのは大変なので、みんなでアンプを共同購入していろんなスタジオに置いていたということも本に書いてありました。では、次にマイルス・バンドですが、ロン・カーターが入るときのエピソードもこの本に書いてあります。簡単に入らなかった毅然とした態度がマイルスに気に入られたみたいです。では1964年2月のライヴ録音のマイルス・バンドの『フォー・アンド・モア』を。ハンコック、トニー・ウィリアムス、ロン・カーターが若さに任せて無茶苦茶なことをやりまくる最初期の音です。曲は「ソー・ホワット」。

♪「So What」/『Four And More』Miles Davis
村井:このライヴはルイジアナとミシシッピの黒人有権者登録を推し進めるための基金活動のベネフィット・コンサートで、ノーギャラなんです。マイルスはそれを知ってたけどミュージシャンたちには言ってなくて、始まる直前に告げたらロン・カーターは楽器をケースにしまいながら「帰る」と。仕方がないからマイルスは自腹でメンバー分の小切手を切ったそうです。
池上:当たり前といえば当たり前なんですけど(笑)、マイルスにそう言えるのは。
村井:ロン・カーターってやっぱりすごい。それ以降マイルスはロン・カーターを信頼して、マイルスがもらうギャラからサイドメン4人分のギャラをロン・カーターに渡す、ロンはそれをきっちり4等分してメンバーに配る──というバンドの会計係もやっていた。運転手もやっていたようで、マイルスはバンドの中でもロンと一番仲がよかった。
池上:今までなかなかそういった話は聞いたことがなかったし、ハンコックもトニーもマイルスから何かを学んだ──という話は聞くんですけど、この本の中でロンは、〈マイルスも俺から学んでいるんだ〉って言っています。
村井:では次に『マイルス・イン・ベルリン』から「枯葉」を聴くんですが、その後で、〈マイルス・バンドは化学実験室だった〉とロンが語っていることについてお話ししたいと思います。
♪「Autumn Leaves」/『Miles In Berlin』Miles Davis
村井:さっきの「ソー・ホワット」はそうでもないんですけどこの「枯葉」はリズム・セクションの3人がやりたい放題。「ソー・ホワット」も所謂モーダルな曲なのでコードというものがなく、あるとすれば半音上がって元に戻るドドリアン・モードってことしかないのでベーシストは何をやっていいのか分からない。テンポが早いこともあってロン・カーターは同じ音のパターンを繰り返すのが結構多いですね。逆にそれに乗って弾く人たちは何をやってもいい、モードの曲でリフを弾くということを割と早めに考えついたのかなと思います。「枯葉」はもっとすごくて、マイルスがテーマのヴァリエーションを展開していくときにロン・カーターは全然曲と関係ないこと、ベースの音を半音ずつ上げて演奏している。曲のコード進行と全然関係ないんですけど、マイルスは気にせずに美しく「枯葉」を吹いて。でも一見無関係にベースが半音ずつ上がっていくと、ある時にものすごい緊張関係が生まれるんです。マイルスの後でウェイン・ショーターが吹く最後のところは、ハンコックがワン・コーラスの間「枯葉」とは関係ない同じコードをずっと弾いて、ロン・カーターもそれに合わせる。でもこの曲は「枯葉」だな──と思わせるのが恐ろしい。そんな実験を毎晩やっていたみたいです。「全部即興でやっていた」ってロンは言ってました。〈マイルスが薬を持ってくる先生で、それを解体したり燃やしたり煮詰めたりするのが俺たちの係で、それを毎晩やっていた〉と。カッコいいですよね。
池上:スタンダードだから聴いてる方も先の進行は分かるんだけど、そうじゃないところに飛んでいっちゃう
村井:それを毎晩やっていて大変だったろうなと思いますけど、マイルスはこの人たちとやるのをすごく喜んでいたみたいですね。で、ロン・カーターってある時期から弦の上で指を滑らせるグリッサンド(奏法)とかスラーをやり始めるんですけど、マイルスとのセッションでの会話を聞くと、マイルスが「ロン、そこでスラーをやってみろ」って指示を出してる。で、ドゥ〜ンって音を出すと、「ああ、それそれ」って言ってる。あのスタイルはマイルスがやらせた説──があるんです。
池上:ロン・カーターっていえばまずはマイルス・バンドの活動が最初のピークでもあるわけです。
村井:ともかくハンコックとトニーとはその後もずっと、トニーが亡くなるまでなにかと共演をしていて、このトリオのスタイルは誰にも真似できないものでした。それで、68年にマイルス・バンドを抜けたロン・カーターはクリード・テイラーが設立したCTIで仕事をたくさんするんです。
池上:この本でもエンジニアのルディ・ヴァン・ゲルダーがロン・カーターの作品の中で自分がやった好きな作品をリストアップしていますが、ほとんどCTIでのものです。
村井:ロン・カーターのアンプで増幅した音が嫌だっていう人がいると思うんですけど、それはCTI時代から始まってます。ロンは自分の音が自分で聞こえないのが嫌、けれどエレクトリック・ベースは上手く弾けないから、その代わりにウッド・ベースを使ってエレクトリック・ベース的なことをやる。そうしないと仕事にならないから。ウッド・ベースに付けるピックアップを注文したり作ってもらったりして、ルディ・ヴァン・ゲルダーとスタジオで実験していたんです。
池上:ロンのトレード・マークというかロン・カーターを決定づける音作り。
村井:音とイントネーションとグリッサンド、この三つがロン・カーターなんだけど……人によって色々好き嫌いはあるようで。ではCTIでのロン・カーター『オール・ブルース』から「ア・フィーリング」を。
♪「A Feeling」/『All Blues』Ron Carter
村井:これはロン・カーターの技がすべて全開。グリッサンドに太く伸びる音──という、僕がジャズを聴き始めた70年代半ばくらい頃のロン・カーターはこれでした。
池上:サウンド的にはマイルス・バンドの頃とは別人といってもいいような。
村井:音色に関してはこの人は頑固。
池上:ピックアップのついた音が嫌いなら俺のところに来るな、って。
村井:ライヴとレコーディングでは全然違うピックアップを使ってるんですね。弦にもすごい拘りがあって、特注品を使っています。ではサイドメンとしてCTIに参加した作品を聴いてみましょう。アルト・サックスのポール・デスモンドがポップスの名曲をたくさんレコーディングしていた頃で、サイモンと ガーファンクルの曲を録音した『明日に架ける橋』というアルバムがあるんですが、その中に収録されている「フィーリング・グルーヴィ(59番街橋の歌)」という曲を。オリジナルのサイモンとガーファンクルではデイヴ・ブルーベック・カルテットのユージン・ライトがベース、ジョー・モレロがドラムで参加しています。ここではロン・カーター、ハービー・ハンコックが入っています。
池上:サウンド的にはマイルス・バンドの頃とは別人といってもいいような。
村井:音色に関してはこの人は頑固。
池上:ピックアップのついた音が嫌いなら俺のところに来るな、って。
村井:ライヴとレコーディングでは全然違うピックアップを使ってるんですね。弦にもすごい拘りがあって、特注品を使っています。ではサイドメンとしてCTIに参加した作品を聴いてみましょう。アルト・サックスのポール・デスモンドがポップスの名曲をたくさんレコーディングしていた頃で、サイモンと ガーファンクルの曲を録音した『明日に架ける橋』というアルバムがあるんですが、その中に収録されている「フィーリング・グルーヴィ(59番街橋の歌)」という曲を。オリジナルのサイモンとガーファンクルではデイヴ・ブルーベック・カルテットのユージン・ライトがベース、ジョー・モレロがドラムで参加しています。ここではロン・カーター、ハービー・ハンコックが入っています。

♪「Feelin’ Groovy」/『Bridge Over Troubled Water』Paul Desmond
村井:かなりベースがフィーチュアされたアレンジで、音も割と生音に近い音ですね。面白いのは、ポール・デスモンドが最初吹いてるときは大人しく普通のランニングをしているんですけど、ハンコックのソロになると突然あのドゥ〜ンって音を弾き始める(笑)。次もCTIのスタンリー・タレンタインの『シュガー』をかけるんですが、これにはエピソードがあって、この作品はスタンリー・タレンタインの割とベタな演歌みたいな作品で……いい曲なんですけど。Cmの曲で最後もCmで終わってたので、ロン・カーターが「あまりにベタベタだからかっこよく変えようぜ」と最後をA♭にしたんです。何か開放感が出てきてスタンリー・タレンタインもいい考えだと思い、他のミュージシャンに「ちょっと俺、考えたんだけど、最後はA♭にしないか」と言ったので、ロン・カーターは「おまえ、いいかげんにしろ!」──という話もこの本に出てきます(笑)。では最後をロン・カーターがA♭にした「シュガー」を。
♪「Sugar」/『Sugar』Stanley Turrentine
村井:ロン・カーターというのはすごく時代を見ていたと思うんです。この音というのはそれまで誰もウッド・ベースでは出せなかった音。CTIってエレクトリック・ベースの全盛期、フュージョンの印象もあるんだけど4ビートもたくさんやっていて、ロン・カーターはどんな音が当時の新しいジャズに合うか──を考えていて、同じようなことをおそらくビリー・コブハムも、トニー・ウィリアムスも考えていたと思う。今にして思えば時代色はありますけど、トニーは70年代後半には26インチという巨大なバスドラを鳴らしたり、ビリー・コブハムはロトタムをずらーっと並べたり、そういう派手なサウンドを考えていた人たちがCTIの中では重用されていて、時代のサウンドでした。で、ロン・カーターは70年代半ばにCTIの専属を辞めてマイルストーンというレーベルに移ります。元リヴァーサイドをやっていたオリン・キープニュースがやっていて、マッコイ・タイナー、ソニー・ロリンズもいました。そこでリーダー・アルバムを作るんですが、おかけする『パステルズ』という作品はクラシック弦楽アンサンブルのジャズに対するロン・カーターの思いの強さを感じさせます。
♪「Pastels」/『Pastels』Ron Carter
村井:「パステルズ」はロン・カーターのオリジナル。明らかにクラシックのアンサンブルで、自分のベースでクラシカルなメロディを美しく歌い上げようという曲なんですけど──。この後90年代にサムシング・エルスというレーベルで何枚かクラシックをやっているんです。「ブランデンブルグ協奏曲」やシベリウスを。それ以降も、一昨年最後に来日したときはチェロ4人とロン・カーターとベースとドラム、ピアノという不思議なメンバーで。未だにこういうのが大好きでライフワークとしてやっています。『ジャズ・タイムス』という雑誌で、評論家たちによる『過大評価されているジャズ・ミュージシャン』という嫌な特集があって、その代表格がロン・カーターだったんです。それに「ブランデンブルグ協奏曲」はバッハに対する冒涜だ──と書かれて、ロン・カーターは怒り狂って〈この文を書いた何某はまったく音楽が分かっとらん! 俺の前で言ってみろ!〉と『ジャズ・タイムス』に投書して、大変な騒ぎになったそうです。ま、この人はクラシック界から締め出されたこともあって、クラシックにはすごい拘りがあるんです。だからかもしれないけれど──聴く方としてはやっぱりジャズをやって欲しい。これも美しく歌い上げてはいるんだけど──微妙なところで音程がね、まあワザとやっている可能性もありますが。ロン・カーターは他の人のバッキングをやるときに比べて、自分の作品のときの方が音程のイントネーションが極端に違う。音楽ってぴったり合うと目立たないけどちょっとズレるとすごい目立つ。意外とそれを考えてないこともないかな、と。では休憩を挟んで後半に入ります。
〜 〜 〜 休憩 〜 〜 〜
映像 1967年11月7日ドイツ
♪「Agitation」/ Miles Davis Quintet
♪「Agitation」/ Miles Davis Quintet

村井:リズム的にはロン・カーターがキープしてるからなんとかなっていて、この頃になるとウェイン・ショーターのソロ辺りはトニー・ウィリアムスはビートをキープするということを放棄しています。ロン・カーターがいないと崩壊してしまう(笑)。
池上:この本の中でもアンカー(錨)とか言われて。
村井:ビーコン(灯台)とも。背が高いし。目標としてロン・カーターを聴いていればなんとかなる。だからトニーとかハンコックにとってはすごくいいベーシストだった。では、ここで70年代後半のトニー・ウィリアムスとのコラボレーションを聴いてみましょうか。この頃になると日本との関わりも強くなってきて、ハンク・ジョーンズのグレイト・ジャズ・トリオに参加、日本のイースト・ウィンドと契約して、日本で大ヒットしました。ハンコックがニューポート・ジャズ・フェスティヴァルで作ったV.S.O.P.の唯一のスタジオ盤も日本で録られてます。日本のジャズ・ファンの間ではロンはヒーロー的な存在で、テレビのコマーシャルに出始めるのもこの頃かな。ロンはジャズ・ファンが思っているより一般に名前が知られてるミュージシャンです。では、トニー・ウィリアムスとの派手なリズム・セクションで、グレイト・ジャズ・トリオのスタジオ盤『KJLH』から「フリーダム・ジャズ・ダンス」。
池上:この本の中でもアンカー(錨)とか言われて。
村井:ビーコン(灯台)とも。背が高いし。目標としてロン・カーターを聴いていればなんとかなる。だからトニーとかハンコックにとってはすごくいいベーシストだった。では、ここで70年代後半のトニー・ウィリアムスとのコラボレーションを聴いてみましょうか。この頃になると日本との関わりも強くなってきて、ハンク・ジョーンズのグレイト・ジャズ・トリオに参加、日本のイースト・ウィンドと契約して、日本で大ヒットしました。ハンコックがニューポート・ジャズ・フェスティヴァルで作ったV.S.O.P.の唯一のスタジオ盤も日本で録られてます。日本のジャズ・ファンの間ではロンはヒーロー的な存在で、テレビのコマーシャルに出始めるのもこの頃かな。ロンはジャズ・ファンが思っているより一般に名前が知られてるミュージシャンです。では、トニー・ウィリアムスとの派手なリズム・セクションで、グレイト・ジャズ・トリオのスタジオ盤『KJLH』から「フリーダム・ジャズ・ダンス」。
♪「Freedom Jazz Dance」/『KJLH』The Great Jazz Trio
村井:ロンとトニーの音圧対決(笑)で当時我々は盛り上がったものです。ロンのベースもフレーズを全く無視したサウンド・エフェクト的なソロで、今にして思えばそうとうアヴァンギャルド。
池上:ハンク・ジョーンズらしからぬ。
村井:ハンク・ジョーンズ若返ってましたね──大変だったと思います(笑)。で、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスにフレディ・ハバードのV.S.O.P.は、1979年日本の「ライヴ・アンダー・ザ・スカイ」で大雨の中の大名演がありますが、その3日後に信濃町のソニーで当時流行りのダイレクト・カッティングでスタジオ盤を作りました。これが『ファイヴ・スターズ』。この第1期V.S.O.P.唯一のスタジオ盤から、トニー・ウィリアムスの曲で「ミュータント・オン・ザ・ビーチ」を聴いてみたいと思います。
♪「Mutants on the Beach」/『Five Stars』V.S.O.P. Quintet
池上:時代の感じもあるんですけど、音が大きいというだけでそれまでのジャズとは違いますね。
村井:ロンも、「長くサスティーンが伸びる音は気に入ってる」って言ってますが、この後90年代に入ってヒップホップの人たちがいち早くロン・カーターを見つけてくる。ドォォォォ〜ン!っていう低音を気に入ったのかな。
池上:ロンの目指したものを分かってくれた
村井:今度はそういう派手じゃないロンのもうひとつの面で、ジム・ホールとのデュオを。どちらかというと大人しい、よりインティメートな作品なんですけど、この2人が東京で大ゲンカをしたという(笑)。
池上:この本に書いてあるんですけど、あの温厚なジム・ホールが真面目なロン・カーターとケンカをするというのは本当に驚きました。ツアー・バンドのリハーサルをロンはやりたかったけれど、ジムはやらなかった。ライヴ当日もロンのソロの途中で曲を止めた──とか、ロンは冷たくされたと怒ってしまってケンカした──というちょっと信じ難い話。
村井:ホテルの入り口で他のミュージシャンがオロオロしている中、60歳を超えた老人2人が掴み合い直前になっていた(笑)。
池上:意外な一面ですが、その後はちゃんと仲直りをしたということです。
村井:では、ロン・カーターがすごく気に入っているというジム・ホールとのライヴ盤から。
♪「All The Thing You Are」/『Live at Village West』Jim Hall, Ron Carter
*ロン・カーターの多彩な側面
村井:ヒップホップとの共演という映像があるので、それを観たいと思います。
池上:1991年にア・トライブ・コールド・クエストの『ロウ・エンド・セオリー』というアルバムにロン・カーターが参加して、そのあとに『レッド・ホット・アンド・クール』というエイズ救済キャンペーンで、ヒップホップとジャズマンの共演ということで、ロンはフランスのラッパーのMCソラーと一緒にやっています
映像
♪「Un Ange En Danger」/ 『Red Hot And Cool/ V.A.』MC Solaar + Ron Carter
♪「Un Ange En Danger」/ 『Red Hot And Cool/ V.A.』MC Solaar + Ron Carter
村井:やっぱりロンは見た目がいいからこういうライヴに呼ばれる。
池上:ジャズ・アイコン、ジャズのレジェンド。そして音がでかい。
村井:サンプリングじゃなくて本人っていうのがいい。
池上:この辺りのエピソードも本には出ていて、ロンの息子マイルスがフランス語を話せたので、MCソラーが変なことを言ったら俺は出ない──って、息子にチェック&通訳をさせた。
村井:ギャングスタ・ラップとかものすごく猥褻なことを言ったら俺は出ない、嫌だと。
池上:その辺が真面目で。
村井:今度はポエトリー・リーディングで、2019年にブルーノートから出た割と新しい作品です。俳優で詩人のダニー・シモンズという人と組んだ『ザ・ブラウン・ビートニク・トームス』のライヴ・アルバムで、ダニー・シモンズが作った詩を朗読するバックでロンはベースを弾いて、その間にロンが今組んでいるトリオ(ギター、ベース、ピアノ)の短い演奏を挟んでいます。
♪「Tender」/『The Brown Beatnik Tomes』Ron Carter, Danny Simmons
♪「Here’s To Oscar」/『The Brown Beatnik Tomes』Ron Carter, Danny Simmons
♪「Here’s To Oscar」/『The Brown Beatnik Tomes』Ron Carter, Danny Simmons
村井:今、ロン・カーターのレギュラー・グループは二つあって、このトリオとフォーサイト・カルテット(サックス、ピアノ、ベース、ドラム)。こちらはスタンダードを中心にメドレーで一曲15分を3〜4曲演奏する4人組。後は一昨年来日したチェロ4人編成を立ち上げようとしたらコロナ禍になってしまった──ということです。でも、まぁ元気ですよね。仕事が好きでしょうがない。で、僕が知ってる限り最新の参加作品が、最初に丸山さんも仰ってたブランディー・ヤンガーという若いハープ奏者のアルバム。この中で2曲ベースを弾いていますので、最後は最新録音でそれを聴いてもらいたいと思います。『サムホエア・ディファレント』から「ビューティフル・イズ・ブラック」。
♪「Beautiful Is Black」/『Somewhere Different』Brandee Younger
村井:ということで、60年以上のロン・カーターの音楽を駆け足で辿ってまいりました、駆け足でも3時間かかりましたけど(笑)。
池上:『「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生』発刊」記念イベント「〜音でたどるロン・カーターの半生〜」、お楽しみいただけましたでしょうか。今日の解説は音楽評論家の村井康司さん。
村井:池上信次さんでした。そしてリモートで丸山京子さん。ありがとうございました。
池上:ありがとうございました。(場内大拍手)

「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生
3,960円

この記事についてのコメントコメントを投稿
この記事へのコメントはまだありません
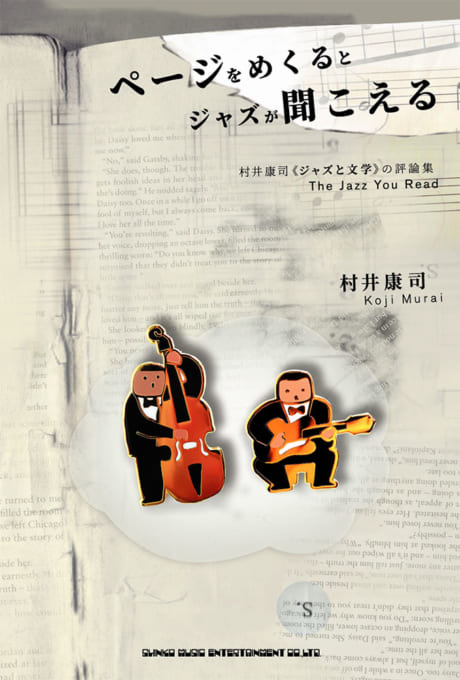

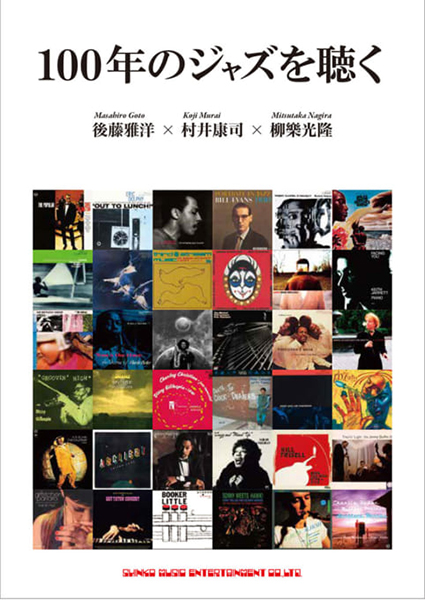

RELATED POSTS
関連記事
-
2025.01.07 クイーン関連 最新ニュース(2026/2/20更新)
-
2024.04.04 ザ・ビートルズ関連 最新ニュース(2026/2/20更新)
-
2024.04.02 【動画】関係者が語る雑誌『ミュージック・ライフ』の歴史【全6本】
-
2023.03.07 直近開催予定のイベントまとめ(2026/2/20更新)
LATEST POSTS
最新記事
-
2025.01.07 クイーン関連 最新ニュース(2026/2/20更新)
-
2024.04.04 ザ・ビートルズ関連 最新ニュース(2026/2/20更新)
-
2024.04.02 【動画】関係者が語る雑誌『ミュージック・ライフ』の歴史【全6本】
-
2023.03.07 直近開催予定のイベントまとめ(2026/2/20更新)
